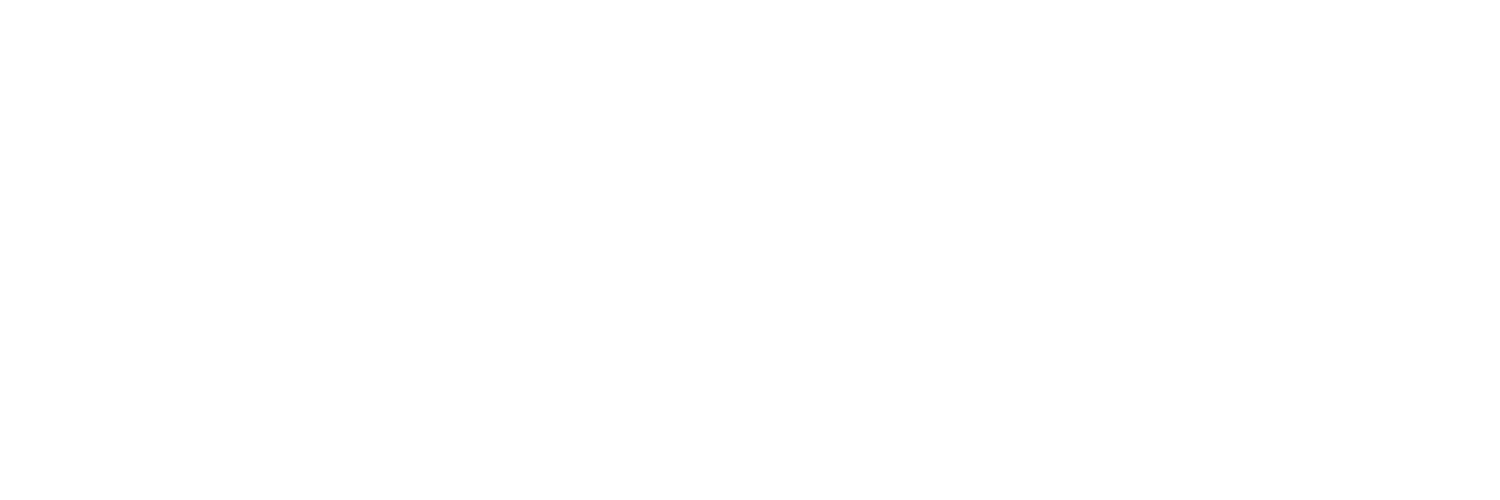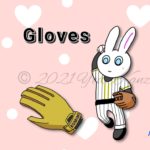走り方は知ってるよ!
急ブレーキ、急発進、急ハンドル(急に傾ける)・・・
「急」の付く操作をしない。ってやつだよね。
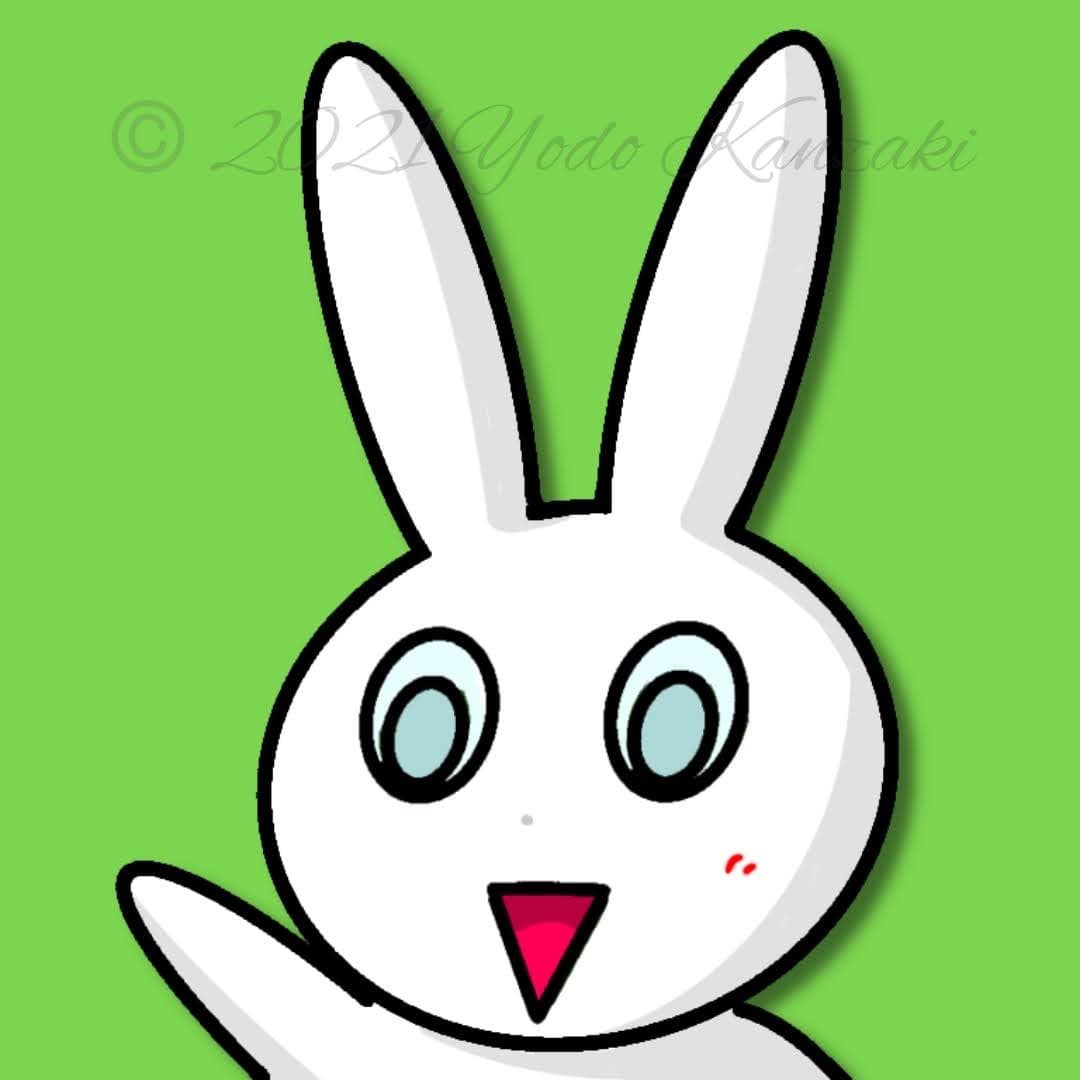
そうですね。
それを踏まえて、3つの重要ポイントがあります。
重要ポイント。
- 曲がるときの動作。
- 足を着く場所。
- タイヤの状態。

まず走行中に注意するポイントから。その後、雨対策について解説します。
目次をクリック・タップで移動できます。
走行時に滑りやすい場所。

中央:マンホール。
右:橋の途中にある継ぎ目。
代表的なものとして、
- 横断歩道や停止線など、道路上のペイント部分(路面標示)。
- マンホール。
- 橋やバイパスにある継ぎ目。
他にも、
・砂や落ち葉がたまっている場所。
・大きい水溜まり。
・道路工事で掘り返された地面。
・道路工事のときに敷かれる鉄板。
これらも滑りやすく、遭遇する可能性が十分にある危険な場所です。
特に滑りやすいのが、マンホールなどの「金属」です。
金属部分を通過するときに「急」な操作は絶対にしないようにして下さい。

初心者は、
「綺麗なアスファルトの路面以外は気を付ける」
このぐらいの感覚がいいでしょう。
滑りやすい場所の走り方。
いちばん最初に書いた通り、「急」の付く動作を控えることを前提として、滑りやすい場所を通過するときの注意点を説明していきます。
車体を傾けていない時。(直進のとき)
アクセルを戻したり、ブレーキをかけたりはせず、アクセル一定のまま穏やかに走行すれば、ほとんど問題なく通過できます。

避けなくていいの?
例えば、遠くのほうにマンホールを見つけて、余裕をもって避けれそう。このような場合は避けたほうがいいですが、余裕のないときは下手に避けないほうが賢明です。
咄嗟に避けようとすると急な動作になりやすいので、アクセル一定で通過するほうが安全です。
・小排気量のバイク。
アクセル・ブレーキ共に、そこまで気を使わなくても滑らずに走れてしまうことがあります。
しかし、絶対に大丈夫なわけではありませんし、ハイパワーのバイクに乗り換えたときに困ることになりますから、ラフなアクセル操作はやめて、慎重に運転したほうがいいでしょう。
傾けて曲がる時。
ポイントは 3つ。
- なるべく傾けないようにする。
- 慎重にアクセルを開ける。
- 避けれそうなら避ける。
1、なるべく傾けないようにする。
曲がる前にしっかりとスピードを落とすことで傾ける量を減らせます。
急ブレーキにならないよう、晴れの日よりも早めに減速を始めて下さい。
※前後のブレーキ配分は後ほど説明します。
2、慎重にアクセルを開ける。
曲がるときは、ある程度向きが変わった段階で アクセルを開けて加速していかなければなりません。
リアタイヤが滑りやすい場所に乗っているときにアクセルを急激に開けると、滑って転倒する可能性が高くなります。
穏やかにゆっくりとアクセルを開けて下さい。
3、避けれそうなら避ける。
少し大回りになるぐらいで避けられそうなら、避けて走ります。
特にマンホールなど金属の場所は出来るだけ避けて走ります。
マンホールを早く発見して避ける為には、車間距離を多めにとっておくことが大事です。
また、避けきれないことも想定して、なるべく車体を立てて曲がれるように手前でしっかりと減速して下さい。
マンホールの上に後輪が乗っているときにアクセルを開けると滑ります。
なるべく後輪が乗っていないときにアクセルを開けるようにします。
気にしてる余裕がないときは、穏やかにアクセルを開けていって下さい。
後輪は「穏やかなアクセル操作で少し滑った」ぐらいだと、転倒せずに耐えられることが多いです。
※出来るだけ車体を傾けていないことが前提です。
滑りやすい場所が長く続く場合。
長い砂利道などを走るときは、まず手前で出来るだけ速度を落とします。
そして普段より高めのギアにして、エンジン回転数を低く保って走行します。。
ギアは低いほどパワーがあるので、普段より ひとつかふたつ高いギアにしておくことで、タイヤに急な力が加わってスリップするのを抑える効果が出ます。
減速するときは、強力でコントロールしにくいフロントブレーキは絶対に使わないようにします。
リアブレーキもなるべく使わず、アクセルをゆっくりと戻して減速します。
駆動力が(エンジンの力が)伝わっているほうが車体は安定するので、アクセルは一気に全部戻しきらずに、ゆっくり少しずつ動かします。
減速が間に合わないときだけ、リアブレーキを軽くかけます。
ステップに踵(かかと)を置くと、微妙なコントロールがしやすくなります。
足を着くときに滑りやすい場所。

右:路肩がアスファルト部分より少し低く、傾斜もキツい。
道路は排水の為に、中央が高く、端に(路肩に)向かって低くなっていくように作られています。(横断勾配)
砂・落ち葉・ゴミなどが流されて路肩に溜まりやすい構造になっています。
砂は晴れの日でも滑りやすいので要注意。
白いコンクリートの路肩(エプロンブロック)は、アスファルト部分よりも傾斜がキツくなっていたり、少し低くなっていることがあり、「足裏がしっかり着かずに滑る」おそれがあります。
網目の鉄のフタ(グレーチング)も、マンホールと同じように非常に滑りやすいので注意が必要です。
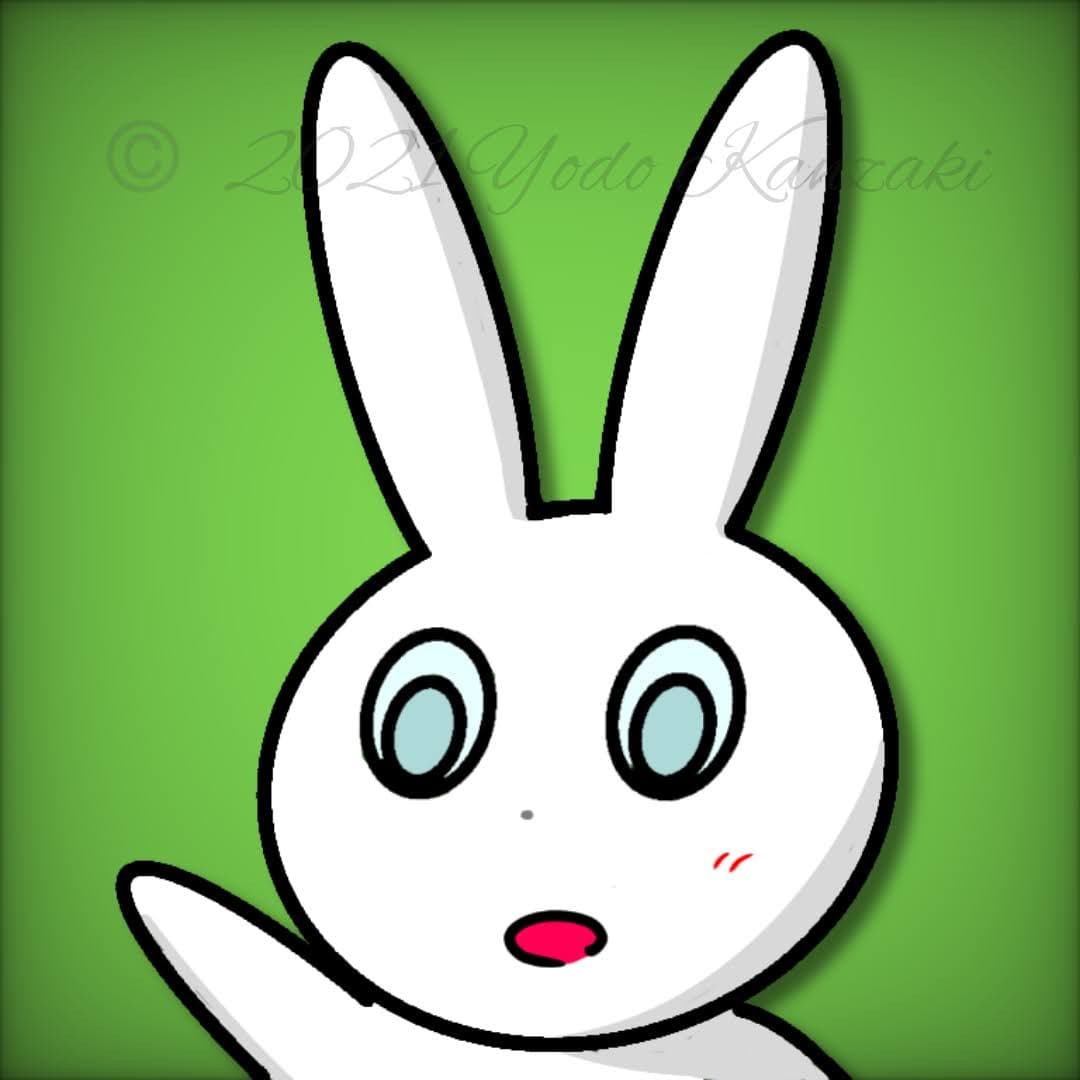
足つきが悪いバイクに乗っている人は、雨天走行で路肩に足を着くのは避けたほうがいいでしょう。
タイヤの状態。
タイヤはゴムで出来ているので、だんだんとすり減っていきます。
すり減っていくとタイヤの溝が浅くなり、排水性能が低下して滑りやすくなります。
また、紫外線で劣化していき、硬くなったり(硬化)、ひび割れが出来たりします。
硬化すると滑りやすくなりますし、グリップ力の低下で停止距離も伸びてしまいます。
ひび割れに関しては、浅いものがほんの少しあるぐらいは問題ありません。
ひび割れが沢山できてきたらバイク屋・タイヤ屋に相談して下さい。
タイヤの寿命。
有名タイヤメーカーのブリヂストン・ダンロップ・ミシュラン、3社ともに明確な年数や走行距離は示していません。
※ブリヂストンによると、車のタイヤは製造後10年、使用開始から5年が目安となっています。
バイク雑誌やネットの情報でも、
・年数:3~5年。
・走行距離:5,000km~25,000km。
と、かなり幅が見られます。
これは、タイヤの種類、普段の走り方や走る道、速度、駐輪環境などによって変わってくるからです。
タイヤメーカーは、
日常的に点検を行い、次で説明するスリップサインや、ひび割れなどから判断する。
そして、分かりにくいときはバイク屋・タイヤ屋に相談するようにと推奨しています。
スリップサイン。

右:スリップサインの場所を示す三角マーク。
タイヤの溝の中にある小さな出っ張りが「スリップサイン」です。
出っ張りの高さは0.8mmで、他の部分よりも溝の深さが浅くなります。
※車(普通車)は1.6mmです。
タイヤの横の三角マークでスリップサインのある場所が分かるようになっています。
一般的に三角マーク(スリップサイン)は 4から6ヶ所、そこそこ均等な間隔で設けられています。
※タイヤの溝は複雑な形状の為、完全に均等な間隔にはなりません。
タイヤがすり減っていき、スリップサインと溝が同じ高さになる(スリップサインが出る)と排水性能が限界で、タイヤ交換が必要となります。

絶対にタイヤは交換しなくちゃいけないの?
スリップサインが1ヶ所でも出た状態で走行すると、「整備不良(制動装置等)違反」とみなされる可能性があります。
参考リンク:e-GOV 法令検索。道路交通法第62条。 別タブで開きます。
参考リンク:e-GOV 法令検索。道路運送車両法。 別タブで開きます。
二輪車は、反則金7,000円・違反点数2点。
原付は、反則金6,000円・違反点数2点。
が課せられます。
なにより危険ですから、スリップサインが出そうになってきたらタイヤを交換しましょう。
| 車種 | 反則金 | 違反点数 |
|---|---|---|
| 大型車 | 12,000円 | 2点 |
| 普通車 | 9,000円 | 2点 |
| 二輪車 | 7,000円 | 2点 |
| 原付 | 6,000円 | 2点 |
タイヤの点検は日常点検の項目のひとつです。
空気圧。

空気圧が高すぎても低すぎても、タイヤの性能を十分に発揮することは出来ません。
空気圧が高いとタイヤの接地面が減り、排水性能やブレーキ性能が低下します。
空気圧が低い場合も排水性能を十分に発揮できず、※ハイドロプレーニング現象が起こりやすくなります。
※ハイドロプレーニング現象:濡れた路面を走行中、タイヤが排水性能を越えるとタイヤの下に水が入り込んで浮いたようになってしまう現象。ブレーキもアクセルも効きにくくなります。
1ヶ月に1回程度、空気圧をチェックすることが推奨されています。
ブレーキ・アクセル操作について。
雨の日の急ブレーキが危険なことは、多くの人が想像できると思います。
しかし、アクセルを戻すことで減速するエンジンブレーキのことは忘れがちです。
急ブレーキだけでなく、急なアクセル操作も控えるようにしましょう。
通常、排気量の大きいバイクほどエンジンブレーキが強力です。

大排気量のバイクでの雨天走行は、穏やかなアクセル操作を心掛けて下さい。
前後のブレーキ配分。
晴れの日。
※前8:後2。もしくは 前7:後3。
雨の日。
前6:後4。
雨の日は、リアブレーキを少し多めに使うと上手く止まれます。
リアブレーキはロック(ピタッと止まる)しやすいので、強くかけるというよりは、多めに使うという感覚で操作するのがおすすめです。
※路面の滑りやすさ(摩擦係数)と、慣性の力で前に移動する重量から考えた前後のブレーキ効力での計算では、前8:後2。
教習所では、前7:後3と教えられることが多いようです。
ABS。
ABSはタイヤがロックする(ピタッと止まる)のを防いでくれる装置です。
A アンチロック。B ブレーキ。S システム。
タイヤが滑って転倒するリスクを大きく下げることが出来ます。
2018年10月から126cc以上の新型車に搭載が義務化されています。
2021年10月から126cc以上の全ての新車に(長年販売されているモデルなどにも)搭載が義務化されました。
125ccまでのバイクは、ABSか※CBS(コンビブレーキシステム)の搭載が義務化されています。
※CBS:前後連動のブレーキシステム。前ブレーキだけかけても、後ろブレーキだけかけても、同時に前後のブレーキが作動します。
急ブレーキでタイヤがピタッと止まってしまうことは防げますが、タイヤの回転が一気に遅くなることは防げません。
タイヤの回転が急に変わるだけでもスリップするおそれがあります。
ABSが付いていても、雨の日は なるべく急ブレーキをかけないように運転して下さい。
TCS。トラクションコントロールシステム。
アクセルを開けすぎてタイヤがスリップしたとき・スリップしそうなときに、自動でパワーを抑えてくれる装置です。
スリップして転倒するリスクを大きく減らすことが出来ます。
ABSと同じように、タイヤの回転が急に早くなることを完全には防げません。
TCSが故障したり、搭載されていないバイクに乗ったときのことも考えて、普段から雑なアクセル操作はしないようにするのが賢明です。
ヘルメットについて。

シールド(前面の透明のカバー)が無いと雨が顔に当たってしまいます。
雨が強いときは、目を開けられないこともあります。
冬はめちゃくちゃ寒いです。
雨の日でもバイクに乗るなら、シールド付きのヘルメットは必須です。
ピンロックシート。
シールドとの間に僅かな隙間を作りながら張り付けることが出来るシートです。
かなり曇りを抑えることが出来ます。
曇る原理をざっくり言うと、シールド外側と内側の温度の違いで曇ります。
シールドとピンロックシートの隙間にある空気が断熱材となり、温度差を少なくして曇りを抑えます。
高い効果がある為、多くのメーカーがヘルメットに付属、又は別売りオプション品を取り付けられるようにしています。
クラシック系には採用されていないこともありますが、色々なシールドに付けられる汎用品もあります。
シールドの撥水剤・くもり止め。

右:ヘルメットのシールド用くもり止め。
雨の日はシールドが曇りやすくなります(シールド内側)。
雨がシールドに沢山残ったままだと前が見えにくくなります(シールド外側)。
特に くもりは簡単には取れないので、ピンロックシートが無い場合、曇り対策はかなり重要です。
撥水剤はシールドの外側、くもり止めはシールドの内側に使います。
どちらもヘルメット専用品がありますが、他のものでも代用できます。
ただし、注意点が 2つ。
- 樹脂に使えるもので透明なものを使用する。
一般的にヘルメットのシールドは、ポリカーボネートという樹脂(プラスチック)で出来ています。
車の曇り止めや撥水剤は、ガラスにしか使えないものが多いので注意して下さい。
- 中性のものを使うこと。
ポリカーボネートはアルカリ性に弱く、酸性にも少しだけ弱い素材です。
有名な代用品。
曇り対策で有名なのは、界面活性剤入りで中性の「食器用洗剤」を使う方法です。
一般的に曇り止めのメイン成分は「界面活性剤」です。
洗濯洗剤やハンドソープなどにも界面活性剤は入っていますが、使いやすさやコスパを考えると、食器用洗剤がおすすめです。
手順。
1、洗剤をティッシュに1~2滴たらす。
2、シールドに塗り込む。
3、ギラつきが消えるまでティッシュや柔らかい布で拭き取る。
かなりコスパがいいのですが、持続時間が短いというデメリットがあります。
大型のブレスガードで曇り対策。

左下:ショウエイ エアーマスク3。(通気用の穴あけ加工をしています)
右:エアーマスク3取り付けイメージ。
息がシールドにかかりにくくして曇りを抑えるパーツを「ブレスガード」と言います。
※アライは「ノーズディフレクター」。メーカーによって名前が違うことがあります。
有名メーカーはオプションで大型のブレスガードを販売しています。
大型のものに交換することで、息がほとんど かからなくなって、曇りをかなり抑えることが出来ます。
眼鏡の曇りを抑える効果もあります。
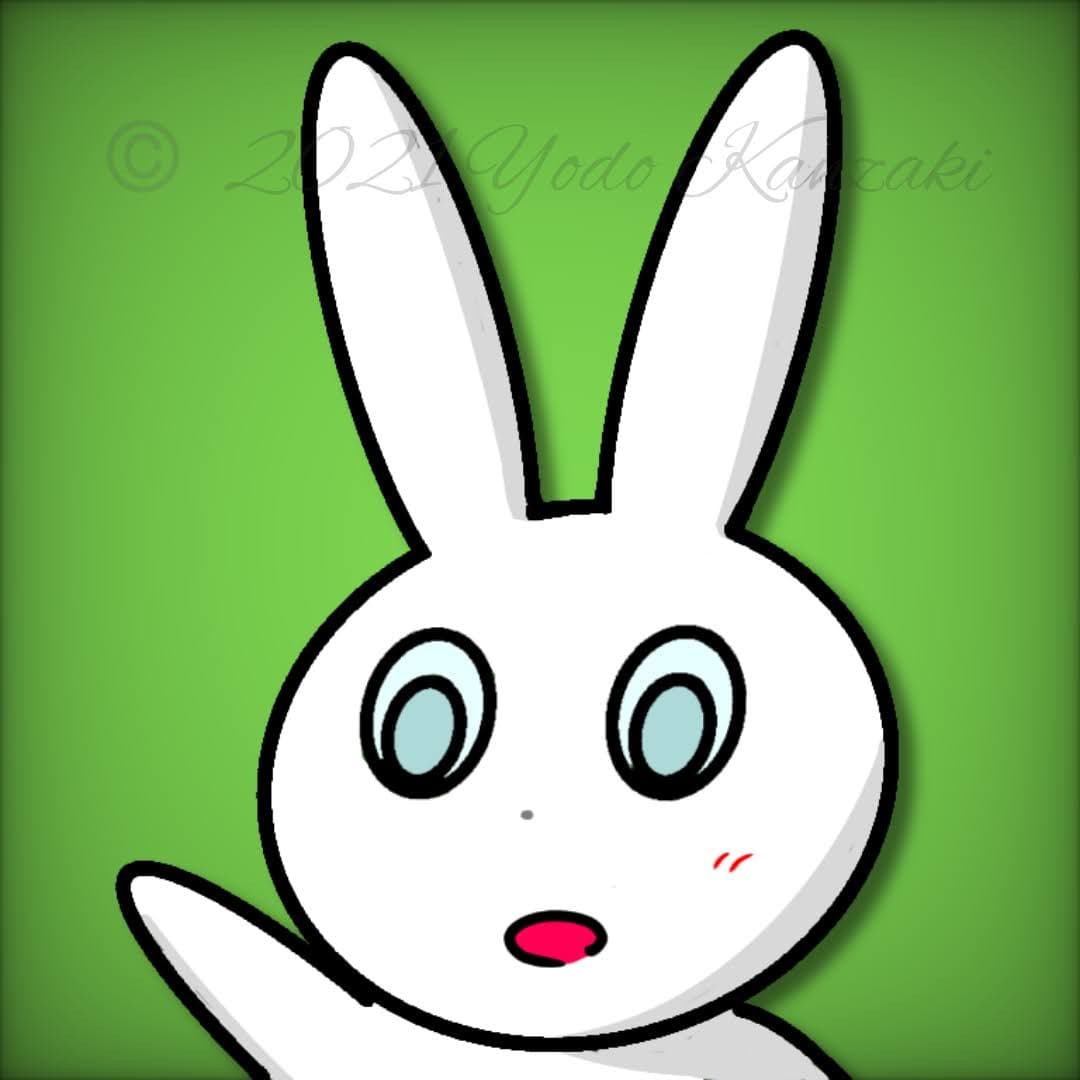
ヘルメットをかぶるとき、外すとき顔に当たる。
という、ちょっとしたデメリットはあります。
※基本的にフルフェイス用です。
構造上、オープンフェイス(ジェットヘルメット)には付けられません。
顎部分を開けられるシステムヘルメットは開けるときに干渉する可能性があります。
眼鏡の曇り対策。

眼鏡はシールドよりも曇りやすく、曇りが取れにくいので対策は必須です。
眼鏡用の曇り止めだけでもある程度の効果は見込めますが、ひとつ上で紹介した「大型のブレスガード」を併用すれば、かなり曇りを抑えられます。
バックミラーの撥水。

ミラーは走行風が当たりにくく、雨粒が残ってしまいがちです。
ミラーは凝視するものではなく、チラッと一瞬だけ見たりするものなので、少し見えにくいだけでも大きな影響が出ます。
ガラスに使える撥水剤や、ミラーに張り付けるフィルムなどで対策します。
どちらも車用のものが流用できます。
撥水剤は数百円から、フィルムは100円からと低価格。
忘れがちですが、安全運転に直結するので ぜひ揃えておきましょう。
レインウェアについて。

防水性・透湿性(汗の湿気を排出)・耐久性・携帯性・見た目・使いやすさ・値段。
複数の要素を兼ね備えるレインウェアは少ないので、まず使用状況に応じて何を重視すればいいのかを考ます。
例。
- 基本、雨の日はツーリングに行かない。
収納時にコンパクトになるバイク用レインウェア。
- 雨でもツーリングに行く。
透湿防水のバイク用レインウェア。
- 通勤、通学。
なるべく低価格のバイク用レインウェア。
頻繁に使うと寿命が短くなりがちなので、安い製品がおすすめです。
- スクーターで通勤、通学。
ワークマンやホームセンターの激安バイク用レインウェア。
どちらも値段なりに作りが甘いので、乗車姿勢がキツくないスクーターにおすすめです。
素材。
- PU (ポリウレタン)。
※透湿防水レインウェアによく使われる素材。
寿命は2~3年。使用回数が少なければ5年以上もつこともあります。
- PVC (ポリ塩化ビニル)。
値段が安くPU(ポリウレタン)より耐久性が高いという特徴があります。
ただし、透湿性はありません。
- テフロン。
透湿防水の高級素材として有名なゴアテックスに使われている素材です。
耐久性が高く、定期的な洗濯などしっかり手入れをしていれば寿命は10年以上。
ただし値段も高いです。
※透湿防水:雨は防ぐが、汗の湿気は通す素材のこと。汗で蒸れるのを軽減できます。
バイク用と一般用の違い。
・バイク用はパンツの裾がかなり長い。
シートに座ると股部分が押さえられ裾が上がって足首が出ます。
ステップに足を乗せる為に膝を曲げると裾が大きく上がって更に足首が出ます。
バイク用以外のレインウェアを使うなら、足首が出てしまうことを前提にした対策を行う必要があります。
・バイク用は乗車姿勢に合わせて裁断されている。
膝を曲げて、手を前に出してハンドルを持った形で突っ張たりしないように作られています。
一般用のレインウェアで乗車姿勢がキツいバイクに乗ると、手首や足首が出てしまい、腕や肩、膝あたりが突っ張ってしまいます。
・バイク用はバタつき防止機能がある。
バタつきは不快ですし、空気抵抗が増えて疲れやすくなります。強風に煽られやすくなります。
高速道路や流れの早い道路を通るなら、風でのバタつきを抑えることはかなり重要です。
グローブについて。

防水性・透湿性(汗の湿気を逃がす)・耐久性・操作性・見た目・値段。
レインウェアと同じく複数の要素を兼ね備えるのは難しいので、 使用状況に応じて何を重視すればいいのかを考ます。
例。
- 基本、雨の日はツーリングに行かない。
操作性重視のバイク用 透湿防水グローブ。
夏は操作性重視のバイク用グローブ プラス 緊急用の防水グローブ。
- 雨でもツーリングに行く。
操作性重視のバイク用 透湿防水グローブ。
プラス 緊急用として防水性能重視のバイク用グローブ。
- 通勤、通学。
防水性重視のバイク用ネオプレングローブ プラス 汗を吸うインナー手袋。
コスパ重視の分厚いゴム手袋 プラス 汗を吸うインナー手袋。
冬はハンドルカバー併用。
- 出来る限り濡れたくない。
防水性重視のバイク用ネオプレングローブ。
分厚いゴム手袋。
ハンドルカバー プラス 透湿防水グローブ。
通勤・通学の味方、分厚いゴム手袋。

中央:耐油手袋、黒。
右:透湿防水の耐油手袋、テムレス。
「耐油」「ニトリル」などと書かれたゴム手袋は、厚手で防水性・耐久性バツグンです。
値段も200円から600円ほど。
ただし通気性はありません。
夏も冬もインナー手袋をしたほうが快適です。
「テムレス」という有名な透湿防水の手袋もありますが、テムレスはかなり薄手です。
蒸れやすい夏用に向いています。
指を曲げた形で作られている製品が多く、ハンドルを握っても突っ張りにくくなっています。
ゴムなのでグリップ力も悪くなく、アクセル・レバー操作も何とかこなせます。

見た目は最悪ですが、黒色や茶色の耐油手袋もあります。青色よりちょっとマシ?
靴について。

中央:非防水のライディングシューズ。
右:防水ソックス。
チェンジペダル(シフトペダル)のあるバイクは、バイク用の防水シューズや防水ブーツにしておかないと、ペダル操作で靴が痛みます。
・通勤、通学で普通の靴を履きたい場合。
「シフトガード」「シフトパッド」と呼ばれるパッドを靴やペダルに取り付けて対処することも可能です。
ただし、靴自体の防水対策が必要となります。
靴に被せる「シューズカバー」「ブーツカバー」という製品があります。
バイク用のブーツカバーなら、ペダル部分にパッドが付いています。
ただし、ブーツカバーは耐久性が低いものが多いです。
また、歩くとすぐに底が擦りきれるので、乗り降りの度に着脱する手間がかかります。
外した後の収納場所も必要です。
もろもろの手間を考えると、バイク用のシューズで走行して、着いたら履き替えるほうが楽なことが多いでしょう。
・スクーター。
スクーターの場合は 操作性を気にする必要がない為、長靴などでも大丈夫です。
普通の長靴は柔らかくて安全性が低いので、作業用のガッチリした長靴がおすすめです。
バッグ類。

ツーリングでは、使いやすさや車体への取り付けやすさが重要ですが、通勤・通学では見た目や本体の防水性能も重要になってきます。
通常、防水性能を高くすると (しっかり閉じないといけない為)、開け閉めに時間がかかります。
また、大きく開くことが出来ない作りとなります。
荷物の出し入れがやりにくくなるので、防水性能か使い勝手かをよく考えて選ぶようにして下さい。
薄手のリュックやメッセンジャーバッグなら、レインウェアの中に入れておける可能性があります。
電子機器。

ETC・USB電源・ドライブレコーダー・スマホ。
バイクに取り付ける電子機器に関しては、説明書に従うのが無難です。
小雨なら大丈夫でも大雨や高速道路走行では使えないという製品もあるので説明書や製品仕様をよく確認して下さい。
面倒ですが、大雨の高速道路走行では「取り外す」といったことも必要となってきます。
スマホなどは防水ケースに入れたりして対処できる場合もあります。
サビ対策。

雨で濡れたまま放っておくと、サビが発生しやすくなります。
雨天走行の後は、サビ対策をしておきましょう。
汚れ具合によって、対処法が変わります。
- ほとんど汚れていない。
水分の拭き取り。
- 少し汚れている。
水で洗い流してから水分の拭き取り。
- かなり汚れている。
洗車。
拭き取り。

中央2つ:セームタオル。
右:ペーパーウエス。
洗車用のウエス(タオル)などで濡れている場所を拭きます。
ホイールやチェーンの近くなど汚れがひどい場所は、使い捨てのペーパーウエスがあると便利です。
水で流してから拭き取り。

ホースが届かない場合、バケツやじょうろでもいいのですが、個人的にはスプレーボトルが一押しです。
上から沢山の水をかけたいときは、スブレーノズルを外してジャバジャバとかけます。
上から水をかけにくい場所はスプレーノズルを付けてスプレーします。
洗剤を入れたものと、水を入れたものを2つ用意すれば、軽い洗車も可能です。
洗車に関しての詳細は、こちらをご覧ください。
チェーン清掃。

雨天走行の後は、チェーン清掃することが推奨されています。
通勤、通学で雨のあとに毎回チェーン清掃するのは たいへんです。
・あまり濡れていないときは、雨と汚れをウエスで拭き取る。
・少し濡れてしまったときは、ウエスで拭き取ってチェーンオイル塗布。
・かなり濡れてしまったときは、しっかりとチェーン清掃。
といったように、ある程度の妥協をしてもいいのではないでしょうか。
私はこんな感じで特に問題は感じませんでしたが、どのぐらい妥協するかは自己責任でお願いします。
雨でも乗らなければならない通勤、通学でスクーターがよく使われる訳。
- 金属部品が少なめでサビ対策が楽。
- チェーン清掃をしなくていい。
- 荷物をシート下に入れれる。バッグ類の雨対策が不要。
時間がかかるチェーン清掃、サビ落としが必要ないというのは、かなり大きなポイントです。
メンテナンスが大好きな人にはデメリットとも言えますが・・・
バイクカバー。

水分が残ったままバイクカバーをかけると、よりサビやすくなってしまいます。
しっかり拭き取ってから かけるようにして下さい。
どうしても時間がないときは、下側を少しめくって出来るだけ湿気が籠りにくいようにします。
その後、なるべく早い段階でカバーを外して水分を拭き取ります。
カバーをめくった状態は防犯の面でもよくないので、元に戻すのを忘れないようにしましょう。
所長から一言。(まとめ)

滑りやすい場所の通過方法。
- 直線。
アクセル一定で通過。
余裕をもって避けれそうなら避ける。
- 曲がるとき。
手前でしっかり減速して出来るだけ傾けないようにする。
穏やかにアクセルを開けてカーブを抜けていく。
マンホール(金属の場所)はなるべく避ける。
マンホールを発見する為に車間距離を多めにとる。

ヘルメットはシールド付きのものを使用。
シールドや眼鏡の曇り対策も必要。
ウェア類は、使用用途から重視したい機能を考えて選ぶ。
濡れたままだとサビやすいので、水分を拭き取ろう。
汚れが酷い場合は、洗車とチェーン清掃。